『どうする家康』第10回のタイトルは「側室をどうする」。
家康(松本潤)が側室をとることになった。瀬名(有村架純)と於大(松嶋菜々子)は不愛想だが気の利く侍女・お葉を候補に選ぶ。ところが彼女は怪しい行動を繰り返す!?
舞台は戦国時代。当然のことながら多くの城郭たちが物語には登場します。
本記事では『どうする家康』第10回に登場する城郭たちを紹介し、物語の背景などを城郭の観点から補足解説いたします。
『どうする家康』第10回に登場する城郭たち
- 岡崎城
- 引馬城
- 上ノ郷城
- 小牧山城
- 今川館(駿府城)
- 躑躅ヶ崎館
お話の舞台はほぼ岡崎城ですが、周囲にきな臭い動きが発生しているため、他の城が少しだけ登場します。
岡崎城
岡崎城はいつも通り登場しますが、瀬名が住んだ岡崎城外の築山が初めて登場します。

築山があったのは、現在のNTT西日本岡崎ビルのあたりだったといわれています。
岡崎城から約1kmの距離。
ここにあった瀬名が住んでいたかも?と言われている建物は、総持尼寺の築山稲荷として移築されています。
 城主 城山塔子
城主 城山塔子築山稲荷には、今川家紋がついているらしく、一度行ってみたいです。
岡崎城について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください


引間城


今川の旗と立派な門のある引間城
引間城は現在の浜松城とは道を挟んで向かい側にありますが、家康が浜松城を建てたときは、浜松城の一部になっていました。
引間城城主である飯尾家は、今川義元の時代、今川氏の家臣であると同時に独立した有力国衆であり、今川氏にとって西側の外交窓口でもありました。
今川氏親が引間城を攻めた時も、徳川家康が引間城を攻めた時も、なかなか落ちずに攻めあぐねています。かなり堅固な城だったのでしょう。


引間城跡地の一角(本曲輪?)には現在東照宮が建てられています。
東照宮のある場所は小高い丘になっており、ちょっとした急斜面を登らなければいけません。切岸と思われる崖が残っているぐらいです。
浜松城に行った際は、引間城にもお立ち寄りください。


上ノ郷城
上ノ郷城は、回想のみの一瞬だけの登場。過去回(第6回)のワンシーンが再登場したに過ぎません。
上ノ郷城について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。


小牧山城


弓稽古をする織田信長
いつの間にか信長の本拠地が清州城から小牧山城に移っています。
桶狭間の戦いの3年後の1563年に小牧山城に移り、1657年には岐阜城に移っています。
現在の小牧山城
頂上にある天守は天守ではなく、天守風の外観をした博物館。信長の時代も家康の時代も、物見櫓こそあれ天守はありませんでした。
発掘調査により、総石垣の城であったことはわかっています。


今川館(駿府城)
今川家臣で国衆の飯尾連龍が駿府に呼び出され、暗殺されます。
不忠の疑いを抱いた家臣を呼び出して謀殺するというシーンは、演出のためか、霧が立ち込めています。霧の中を、岡部元信が近より、連龍を斬り殺します。
今川館は駿府城の下。その全貌は明らかにはなっていませんが、発掘調査により少しだけその姿がわかっています。


駿府城について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください


躑躅ヶ崎館
躑躅ヶ崎館では、武田信玄が今川家臣たちを調略せよという命令を下しています。
実際に黄金を使用して凋落していったのかどうかは分かりませんが、この時代の甲斐国は金を掘り尽くしてしまっていたので、なけなしの金を見せているのかもしれません。
躑躅ヶ崎館の水堀
背後に要害山城のある山があることは確かです。今は木々に覆われているのかもしれませんが、当時は見晴らしを良くするために、木は伐採されていたはずです。
前田左衛門佐, Public domain, via Wikimedia Commons


第10回「側室をどうする」のあらすじ
冒頭で、家康は酒井忠次とともに引馬城の飯尾連龍と面会します。
家康にとって、連龍の妻は鵜殿長照の妹であり、家康の妻である瀬名の幼馴染。鵜殿長照を家康が討ち取ってしまったことが、家康にとっての気がかりの様子。



私は今川と戦をしたいのではなく、今川と松平の間を取り持ちたいのです。
飯尾家は独立した国衆でると同時に今川家臣でもあり、今川家にとって西側の外交窓口の役割を担っていました。飯尾家の立場を考えれば、間を取り持ちたいというのは裏切りではなく当たり前の行動だったのではないでしょうか。
- 渡辺半蔵守綱
- 飯尾連龍
- 松平家康
- 酒井忠次
- 田鶴
- 瀬名
- 鵜殿長照(回想)
- 於大の方
- 織田信長
- お葉
- 登与
- 美代
- お杉
- お梅
- 今川氏真
- 穴山信君
- 柴田勝家
- 山県昌景
- 千代
- 岡部元信
- 木下藤吉郎
- お市の方(回想)
- 武田信玄



岡部元信は登場はしますが、相変わらずセリフはありません。
- 鵜殿長照の妹を妻に持つ飯尾連龍は、今川と松平の間を取り持ちたいと家康と面会する
- 築山に住み始めた瀬名の元に於大の方が訪れ、子を生むために側室を持つことを勧める
- 側室希望者から側室を選ぼうとするも見つからず、城勤めをするお葉の名が挙がる
- お葉は一女をもうけ、ふう(督姫)を出産する
- 木下藤吉郎からお市の方が結婚し、織田信長の動きを知らされる
- 家康と通じたと飯尾連龍が今川氏真に処分される
築山にて
一揆後、民と殿との間を取り持つために岡崎城外の築山の屋敷をもらって住み始めた瀬名。家康が訪れているところに、家康の母である於大の方も訪れます。
嫁と姑の微妙な空気が流れ、なんのためにここを訪れたのかと問う家康に対し、於大の方は2人の間に子供が2人しかいないのが気がかりだと答えます。



子をどんどんつくって、あっちとくっつけ、こっちとくっつけ、松平家を盤石なものにしていかねばならぬでしょ。
と側室を持つことを提案。その側室選びは、家康を無視して於大の方と瀬名で進められることになりました。
「側室」という言葉が誕生したのは江戸時代。この時代に側室という言葉はなく「別妻」という言葉が使われており「正室」も「正妻」でした。
そのことを知っている視聴者は少ないので、ドラマでは「側室」を採用しているのだと思います。
別妻は好き勝手に選ばるわけではなく、正妻の許可が必要で、別妻は正妻の管理下にあったことを示すドラマ仕立てになっています。
第10回「側室をどうする」の感想
家康の初めての側室の本名は伝わっておらず、「お葉」という名前は戒名から設定したと思われます。
お葉と殿との間に一女(おふう:督姫)が産まれます。西郡の局には殿との間に1人しか子どもがいないことを、このように解釈してしまうとは……。



斜め上すぎて、ぶっ飛びました。
SNS上でも、賛否両論ありました。レズビアンって……。
鵜殿家の一族
今回登場するお葉(西郡の局)も、飯尾連龍の妻のお田鶴の方も、本当のことはわかっていませんが、鵜殿家の一族です。
側室の西郡の局とお田鶴の方は姉妹と考えられていました。最近の研究では、西郡の局は鵜殿家の分家と考えられており、姉妹ではないようです。



上ノ郷城の戦いで、鵜殿家はお家存続のために今川派と松平派に分かれて戦っているし、西郡の局は松平派の鵜殿家だったのかもしれません。
飯尾連龍
名前だけなら第5回でも登場しています。
引馬城の城主で、今川義元の時代には独立した国衆ではありますが、今川氏の家臣として西側の外交窓口として活躍していた人物です。
氏真の時代になっても、今川氏の外交窓口として働きたいというのであれば、ドラマのように今川と松平の間を取り持ちたいというセリフに納得できます。
史実では、今川氏真が三河に出兵した際に勝手に帰国したり、家康から援軍してもらったりと、明らかに松平氏側についたことが明らかな行動をしています。



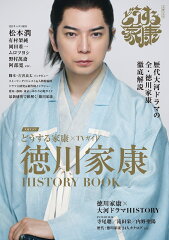

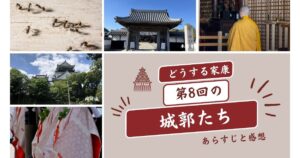



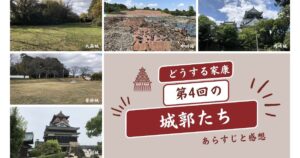
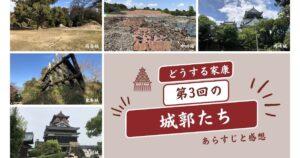
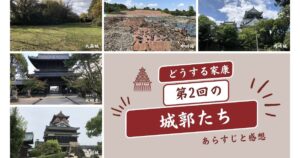
コメント